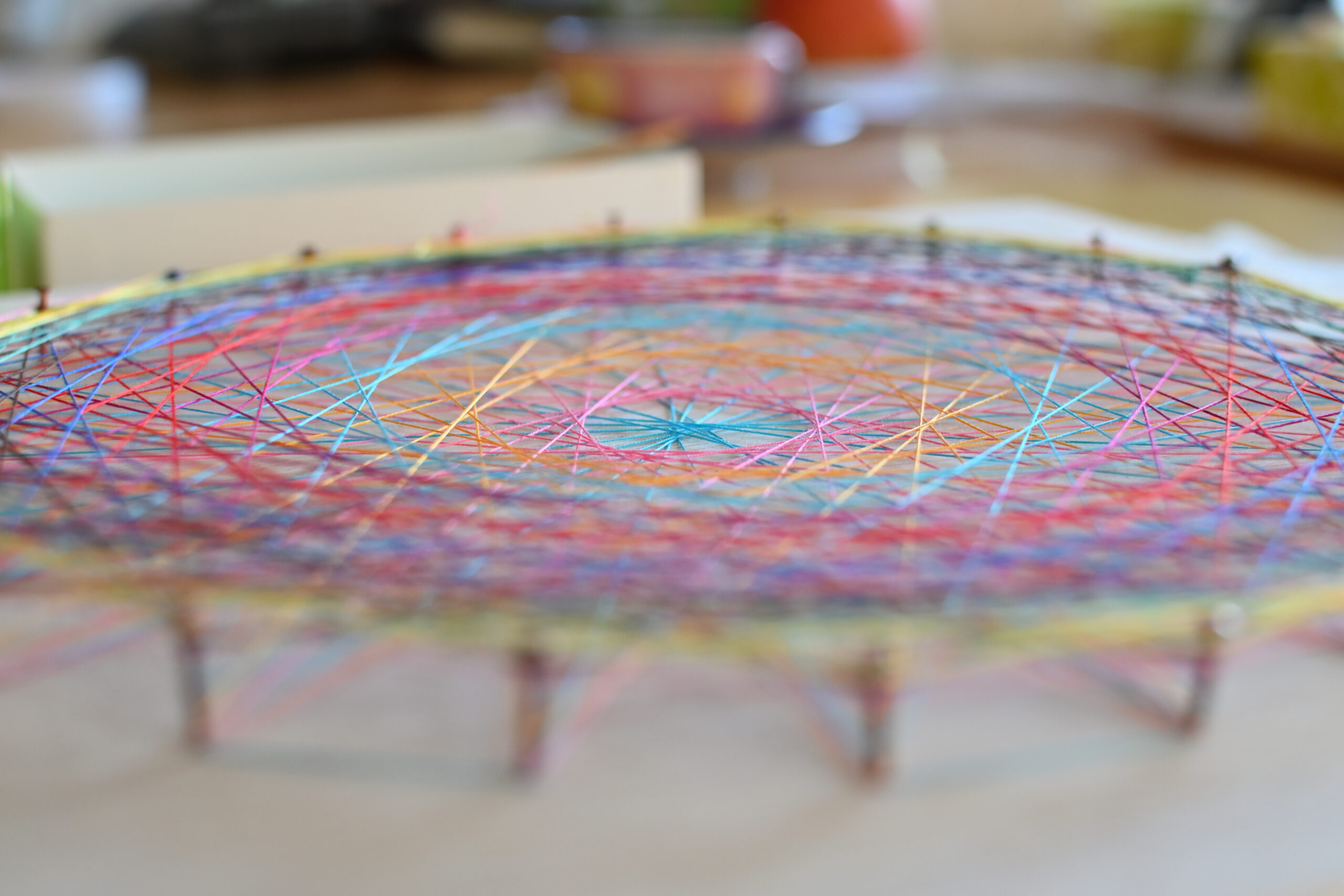子どもに知識を与えることはできても、その子の個性や心の成長をどう支えればいいのか──。
親として、先生として、日々ふと立ち止まるときに浮かんでくる問いかもしれません。
そんな想いに応える形で、世界のあちこちで選ばれてきたのが「シュタイナー教育」です。
20世紀初めに思想家ルドルフ・シュタイナーが提唱したこの教育法は、芸術や自然、日常の体験を通じて、子どもを“ありのままの存在”として育むことを大切にしています。
この記事では、シュタイナー教育の基本理念や特徴、日本の教育との違い、そして子どもの発達段階に応じた学びの仕組みをわかりやすく解説します。
シュタイナー以外の教育(モンテッソーリ・レッジョエミリア等)にもご興味がある方はこちらの記事もあわせてお役立てください。

シュタイナー教育とは?子どもを全人的に育む教育法
シュタイナー教育とは、20世紀初頭にオーストリアの思想家ルドルフ・シュタイナーによって提唱された教育法です。世界では「ワルドルフ教育(Waldorf Education)」とも呼ばれ、現在では70か国以上に約1,200校の学校と約1,800〜1,900の幼稚園が存在する、世界最大級の独立教育運動へと発展しています。
日本には1980年代以降に紹介され、2021年時点で全日制のシュタイナー学校が7校、幼児教育施設が371園設立されています。
その本質は「自由への教育」という理念にあります。子どもを大人の価値観に合わせて早期に知識詰め込み型に育てるのではなく、意志・感情・思考をバランスよく育て、自分の意志で自由に生きられる力を養うことを目指しています。
シュタイナー教育の理念:「自由への教育」
ルドルフ・シュタイナー(1861–1925)は「教育は子どもを社会に従わせるためではなく、子ども自身が自由に生きられる人間になるための準備である」と説きました。
ここでいう自由とは、放任や自己中心ではなく「自ら考え、責任をもって社会に関わる力」を意味します。そのため授業は知識の伝達よりも、芸術・物語・自然体験といった活動を通じて子どもの内面に働きかけることが重視されます。
たとえば黒板一面に描かれた色彩豊かな絵を前に物語を聞き、そこから文字を学ぶ──そんな授業風景が日常的に見られます。
発達観:7年周期で育む「からだ・こころ・あたま」
シュタイナー教育では、人間の成長を7年ごとの段階でとらえます。
- 0〜7歳(幼児期):模倣と遊びを通じて「からだ=意志」を育む
- 7〜14歳(児童期):芸術や物語を通じて「こころ=感情」を育む
- 14〜21歳(青年期):探究や批判的思考を通じて「あたま=思考」を育む
この発達観に基づき、学びの内容や方法も大きく変化します。幼児期には文字や計算の早期教育を行わず、遊びや生活リズムを通じて基礎を育てる。児童期には物語や芸術を通して感情を育み、青年期には学問的・抽象的な探究を深める──この流れが一貫した特徴です。
哲学的背景:ルドルフ・シュタイナーと人智学
シュタイナー教育は、ルドルフ・シュタイナーの思想「人智学(アントロポゾフィー)」を基盤としています。人智学では、人間を肉体・魂・精神の三側面からなる存在と捉え、教育は「人間形成を支える芸術」であると位置づけられます。
そのため、シュタイナー教育は単なる知識習得ではなく、人間全体をどう育むかという視点を常に中心に据えているのです。
世界と日本における広がり
シュタイナー教育は1919年9月7日、ドイツ・シュトゥットガルトに設立された「自由ヴァルドルフ学校」を起点に始まりました。そこからヨーロッパ各国、アメリカ、アジアへと広がり、現在では70か国以上に根付いています。
日本でも1980年代以降、東京・神奈川・愛知などを中心に学校や幼児園が設立され、保護者や教育関係者の支持を得て発展しています。
シュタイナー教育の特徴:独自のカリキュラムと学び方
シュタイナー教育の大きな特徴は、子どもの発達段階に合わせたカリキュラムと、一般的な学校とは異なる独自の授業方法にあります。特に「エポック授業」「自作ノート」「芸術・手仕事・音楽・オイリュトミー」といった実践は、シュタイナー学校ならではの象徴的なスタイルです。
エポック授業:ブロック集中型の学習法
通常の学校では1日に複数の教科を少しずつ学びますが、シュタイナー学校では「エポック授業」と呼ばれる方式を導入しています。
- 朝の約100分を「国語」「算数」「理科」など一つの教科だけに充て、2〜4週間かけて集中的に学ぶ
- その後、一定期間を空けて再び同じ科目を取り上げ、前回の学びを呼び起こしながら発展させる
たとえば、数週間かけてひとつの物語を読み込み、その中に登場する数や図形を題材に算数を学ぶ。こうした体験の積み重ねが、知識を「覚える」以上に「生きた知恵」として定着していきます。
自作ノート:子ども自身がつくる教科書
シュタイナー学校では、一般的な教科書を使いません。代わりに生徒は「エポックノート」と呼ばれる学習帳を作成し、授業で学んだ内容を文章や絵でまとめていきます。
- 算数なら図形や計算をカラフルに描く
- 国語なら物語の挿絵を添えて文章を書く
- 理科なら観察結果をスケッチする
ノートは色彩豊かで、ひとりひとりが創作した「世界に一冊だけの教科書」となり、学びを創造的に定着させる役割を果たします。
芸術・手仕事・音楽・オイリュトミーの重視
シュタイナー教育では、芸術的な活動がカリキュラムの中心に置かれます。
- 美術や工芸:編み物・木工・彫刻などを通じて「手を動かす力」を育む
- 音楽:リコーダーや弦楽器を習い、合唱や合奏で協調性を学ぶ
- オイリュトミー:詩や音楽を身体の動きで表現する独自の身体芸術
- 演劇や詩の朗誦:感情表現や表現力を伸ばす
これらは副次的な活動ではなく、知性の土台を育てる中心的な学びとして位置づけられています。
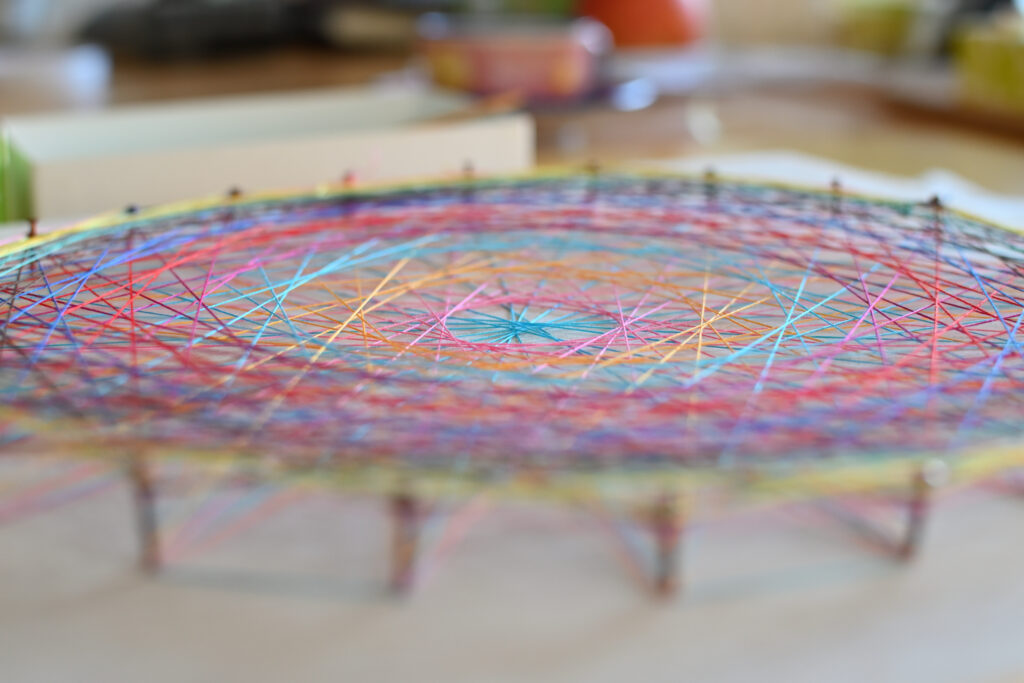
シュタイナー教育における年齢段階ごとの教育内容
シュタイナー教育では、人間の発達を7年ごとに区切り、各段階にふさわしい教育を行うことが重視されます。
幼児期(0〜7歳):遊びと生活リズムで「からだ」を育てる
この時期の子どもは、大人を模倣しながら成長します。
木や羊毛など自然素材のおもちゃを使った自由遊びや、歌・手遊び・季節ごとの行事が日々の中心です。羊毛で小さな人形を作ったり、庭で泥遊びをして自然と触れ合うことも立派な学びとされます。さらに、食事や掃除を先生や仲間と一緒に行うことで、生活そのものが教育になります。
児童期(7〜14歳):物語と芸術で「こころ」を育てる
感情や想像力が育つこの時期には、物語や芸術を通じて学ぶことが中心になります。
- 国語では神話や昔話を先生が語り、その物語をもとに文字を学ぶ
- 算数は九九を歌にして覚えたり、色鉛筆で図形を描きながら数の仕組みを理解する
- 音楽や手仕事を毎日の学びに組み込み、感性を育む
また、1年生から8年生まで担任が持ち上がる「長期的な関わり」が特徴で、人格的な信頼関係を基盤に学びが深まります。
青年期(14〜21歳):探究と批判的思考で「あたま」を育てる
思春期に入ると、子どもは抽象的に考える力を発達させます。
理科は「実験や観察 → 自分で考察 → 理論理解」という流れで進め、文学や歴史は討論や演劇を通じて多角的に理解します。
その集大成が「卒業プロジェクト」です。
生徒は自分でテーマを決め、木工で家具を製作したり、演劇を一から上演したり、社会調査や科学研究を行うなど、一年間かけて探究します。最後には成果を保護者や仲間に発表し、学びを社会に向けて表現する経験を積みます。
シュタイナーと日本の教育との違い
シュタイナー教育と日本の学校教育は、学び方・評価・教師の役割・環境づくりなどに大きな違いがあります。両者の特徴を整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 日本の一般的な教育 | シュタイナー教育 |
| 授業スタイル | 1コマ45分前後、1日5〜6科目を並行学習 | エポック授業:1科目を約2〜4週間集中して学ぶ(朝100分) |
| 教材 | 文科省検定教科書を使用 | 教科書なし。生徒が「エポックノート」を作成 |
| 学力評価 | 定期テストや通知表の数値評価 | テスト・偏差値なし。教師が文章で成長を所見記録 |
| 教師の役割 | 担任は学年ごとに交代。中学校から教科担任制 | 担任が原則1年生〜8年生まで持ち上がり制。教育芸術家として子どもを長期的に導く |
| 芸術・体験 | 美術や音楽は副教科扱い | 美術・音楽・手仕事・オイリュトミーが中心科目。主要教科にも芸術的要素を統合 |
| 学習環境 | ICT機器の活用が進む。家庭学習も重視 | 低学年ではメディアを排除。自然素材の環境と生活リズムを重視 |
| 進学・学力観 | 高校・大学受験を意識。偏差値が中心 | 大学進学率は高いがAO入試や自己推薦が多い。知識よりも主体性や表現力を重視 |
教科書と授業スタイルの違い
日本の学校は「幅広く、少しずつ繰り返す学習」が基本です。一方、シュタイナー学校は一つの科目を徹底的に掘り下げる集中型。この違いにより、学習体験の深さや知識の定着方法が大きく変わります。
学力評価の違い
日本では点数や評定による競争が前提ですが、シュタイナー教育では序列づけを避け、個々の成長を文章で評価します。これは「子どもが比較でなく自己の成長に目を向ける」ことを狙った方法です。
教師の役割の違い
日本の学校では担任が頻繁に変わりますが、シュタイナー学校では1人の教師が約8年間同じ子どもたちを導くのが特徴。人格的な信頼関係を基盤に、学力だけでなく情緒や社会性を長期的に育てます。
学習環境の違い
ICTやデジタル教材が普及する日本に対し、シュタイナー教育では低学年でメディアを極力排除。自然素材の教具や家庭的な環境を整え、五感を使った体験を重視します。
まとめ|多様な教育メソッドを理解する意義
シュタイナー教育は、子どもを「知識だけでなく、からだ・こころ・あたまの全体で育てる」という発想に立った教育法です。
日本の教育との比較を通じて見えてくるのは、学びの方法や子どもとの関わり方には一つの正解があるわけではないということです。
芸術や体験を通じて心を育てるアプローチもあれば、知識習得を重視するアプローチもある。大切なのは、そうした多様な教育メソッドを理解し、それぞれの子どもや現場に合ったかたちで取り入れていく視点です。
私たちフィーノリッケペダゴーは、デンマークをはじめとする北欧の教育文化に学びながら、日本の子どもや大人に必要な「人と人との関わり方」「社会性を育む力」を伝えています。
シュタイナー教育のような世界の教育思想に触れることは、子どもへの理解を深めるだけでなく、教育や子育てに関わる大人自身の学び直しのきっかけにもなるでしょう。
「フィーノリッケペダゴー資格認定講座」は、デンマークの教育専門職「ペダゴー(Pædagog)」の理念と実践を基に、日本の保育・教育現場に適応した民間資格プログラムです。
この講座は、子どもの社会性や感情理解を育むための対話的・実践的なスキルを習得することを目的としています。
\100人以上の教育従事者が実際に体験/